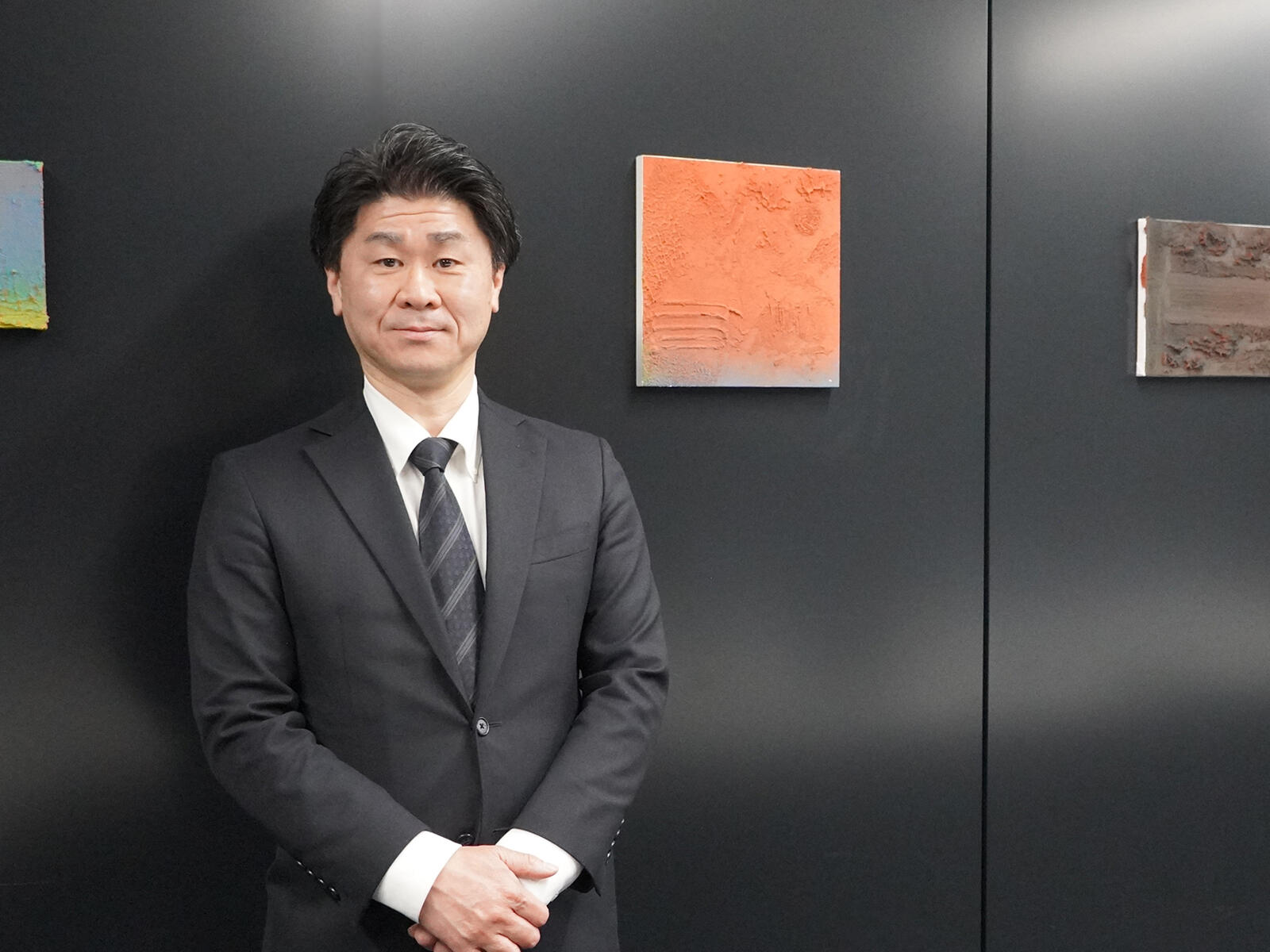
2025.07.04
可視化・最適化に向けた意識改革とCLOの役割|物流の未来をデザインする #4
大きな転換期を迎えている物流業界。フューチャーアーキテクトは、「物流×IT」で社会課題を解決することをミッションに、CLO(Chief Logistics Officer 物流統括管理者)の支援に取り組んでいます。
シリーズ「物流の未来をデザインする」第4回は、経済産業省 商務・サービスグループ 消費・流通政策課長 物流企画室長 平林孝之様をお迎えし、物流課題に対応するデジタル活用のありかたや、2026年度から一定規模以上の荷主企業に選任が義務付けられるCLOへの期待について考察します。
※本記事は2025年4月に行った取材をもとに構成しています。
可視化・最適化に向けた意識改革とCLOの役割
引網 前回「物流改正法が示す、政府と事業者がともに目指すべき方向」の記事では、改正物流効率化法のポイントや物流事業者の課題感とデジタル活用について議論しました。物流最適化に向けて、改正物流効率化法では荷主・物流事業者等の努力義務として、「積載効率の向上等」「荷待ち時間の短縮」「荷役等時間の短縮」の3つが挙げられています。これらの実現に向けたデジタルの活用についてどのようにお考えですか。

平林 デジタル化の取組みについては、「物流革新に向けた政策パッケージ」、「合同会議取りまとめ案」等でご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、積載率向上に向けた複数荷主の貨物の積合せや共同配送、荷待ち時間短縮に向けたトラック予約受付システムの導入等が挙げられます。ただし、デジタル化を推進するためには、まず「データ」をしっかり取得することが必要です。
例えば、ドイツが進める、製造業においてIT技術を取り入れた業態改革を目指す「インダストリー4.0」でも、工場のあらゆる箇所に計測器を導入し、あらゆるデータを取得することから始まります。データの取得を通じて現状を把握し、はじめて改善や対策の方針が明らかになる点は物流も同じです。改正物流効率化法に定める定期報告の義務化はその一つの契機になるのではないでしょうか。
引網 デジタル化と一言にいっても、具体的なソリューションやシステムを導入さえすれば良いわけではなく、事業者の皆様がそれぞれの実情に合わせたロードマップを描く必要があるということですね。フューチャーアーキテクトでもデジタルの活用によりお客様の企業価値を高める取組みを行っていますが、思うところはありますか?
産形 「可視化」が重要という認識は広がっている一方、IT・デジタルでは「投資」も必要になりますので、可視化や最適化でいかに効果を創出できるかが経営の重要なポイントです。
平林 日本企業のとても良いところでもあるのですが、突発事項や緊急事項に対応する柔軟性が、却って業界を変革する阻害要因になっている面があるのかも知れませんね。例えば、物流業界では今日中に配送をお願いしたい、急に荷物が増えてしまった、といった突発事項や緊急事項がどうしても発生しがちですが、そのような場合の価値ある対応には、相応の対価が支払われるべきですね。
CLOへの期待と持続可能な物流の未来
引網 サプライチェーンの可視化・最適化を企業内外でリードし、自社の物流効率化にとどまらず、企業価値の向上につながるロードマップを描くことがCLOの役割の一つと言えそうですね。CLOに期待することについてさらに伺えますか。
平林 2026年4月から特定事業者の荷主にはCLOの選任が義務化されます。CLOに期待する点は、まずは社内の物流に対する意識の向上です。物流部門だけでなく、調達、生産、配送、マーケティング、営業等も含めた全社的な連携とサプライチェーンの統括を行い、他社との外交的役割も担っていただきたいと思います。
例えば、社内の連携が必要な例では、パレタイズが代表的かと思いますが、パレットに適合した商品パッケージの設計、商品開発、商品に合わせた製造ラインの設計等、すべてが一気通貫になることで、理想とされるパレタイゼーションが実現します。こうした社内関係者の調整といった役割も期待したいと考えています。

引網 かつて物流は一義的にはコストとされ、コスト削減が一つのKPIと言えましたが、今後はデザイン・フォー・ロジスティクス(Design For Logistics)をも踏まえた最適化が必要になるという考え方は大変参考になります。
産形 私たちのお客様で、入荷したパレットの積み付けに端数があることが倉庫検品時の課題となっている事例があります。欧米のメーカーではパレットサイズと発注可能な出荷単位を合わせて、価格もパレット単位で設定していますが、日本でも同じことができると思います。物流の現場では、梱包にバーコード表示がないため入出庫の検品に人手と時間がかかるなど、他にも様々な課題があります。
フューチャーでは検品等の作業を効率化する独自のAI-OCRソリューション「Future EdgeAI」を提供していますが、今後はメーカー・発注側ともに、運ぶときや検品するときの荷姿を意識することが必要だと思います。
平林 デジタル化で解決できることと、暗黙的なルールである商習慣と両方の見直しが必要ですね。「物流革新に向けた政策パッケージ」の"3つの柱"の一つに「商習慣の見直し」が入っているのは非常に重要です。効率化を進めるなかで、商習慣も含めどこを見直し、どう改善すればいいかを考えるきっかけになればと思います。
引網 最後に、官民連携による持続可能な物流の将来像を考えていきたいと思います。
平林 政策パッケージの公表や改正物流法をつうじて、各省庁が一体となって政府全体で物流効率化に取り組む姿勢を示すことができた点は一つの大きな成果です。目指す姿を描き、官民のベクトルを合わせられたことで、荷主企業の皆様の姿勢が前向きに変わっていると実感しています。また、物流=コストというこれまでの発想を脱却でき、企業内での意思決定が進めやすくなったという話もあります。
物流を取り巻く状況が変化した先の目指す姿は、究極の共同輸配送を実現する「フィジカルインターネット」です。相互に結び付いた物流ネットワークを基盤に、グローバルなロジスティクスシステムを構築することで、効率性と持続可能性の向上を目指します。政府として2040年の実現に向けた「フィジカルインターネット・ロードマップ」を示しています。
引網 政府も企業も変わっていくなかで、業界横断的な取組みは非常に重要です。デジタルを支える企業として、私たちフューチャーアーキテクトは物流改革をどのように支援していけるでしょうか。
産形 法改正などをきっかけに、非効率な商習慣や商取引の在り方も見直され、サプライチェーンの改革につながっていくはずです。今回の物流改正法ではかつてない良い化学反応が業界で起きていると感じています。CLOがデジタル化に取り組むためには、CEOやCIOがデジタル投資を推進できる戦略が必要です。私たちはCLOをパートナーとしてサポートしつつ、皆様の物流の協調領域・競争領域をお支えしていきたいと考えています。
引網 平林課長、本日はありがとうございました。



