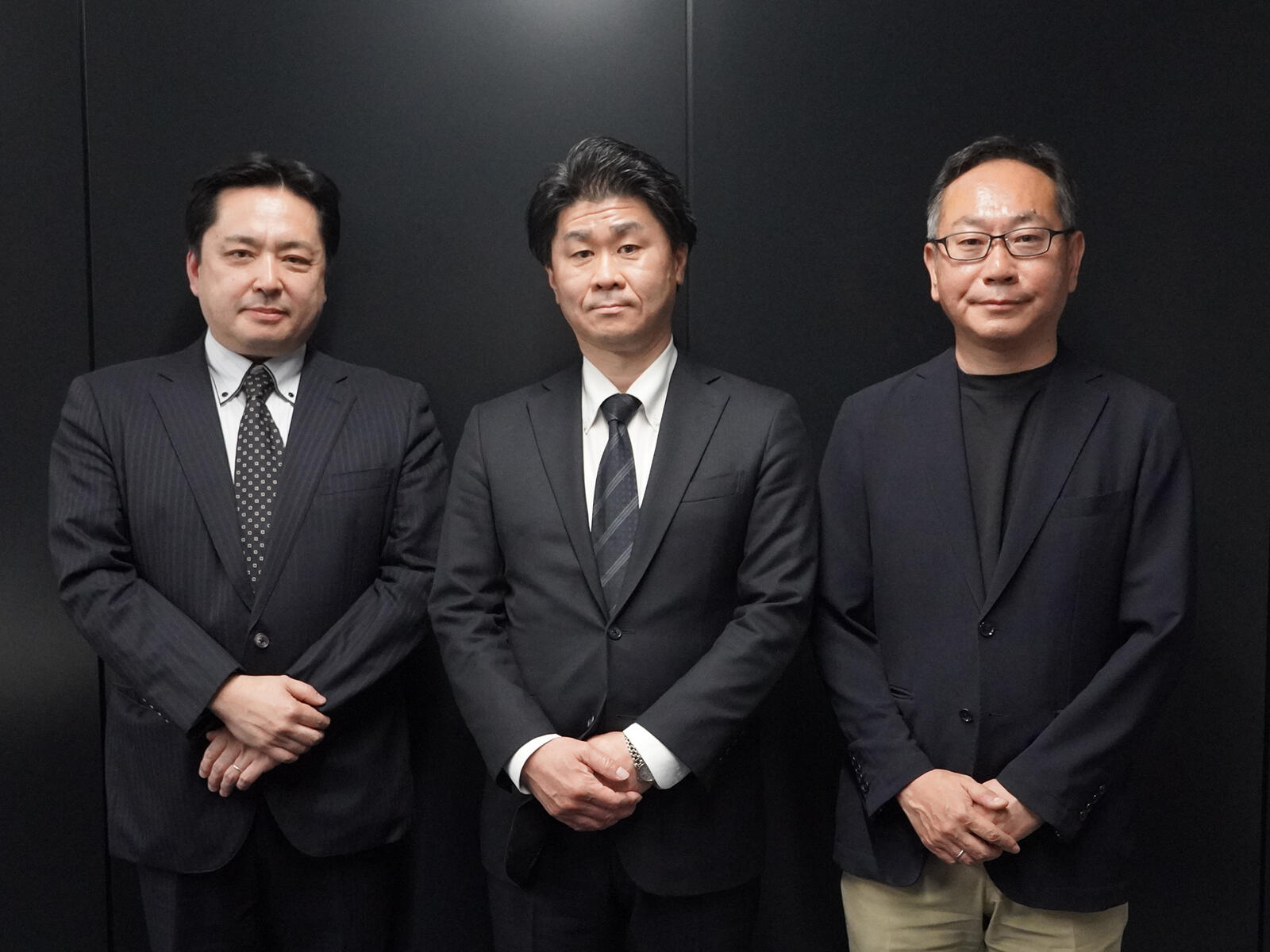
2025.07.02
物流改正法が示す、政府と事業者がともに目指すべき方向|物流の未来をデザインする #3
大きな転換期を迎えている物流業界。フューチャーアーキテクトは、「物流×IT」で社会課題を解決することをミッションに、CLO(Chief Logistics Officer 物流統括管理者)の支援に取り組んでいます。
シリーズ「物流の未来をデザインする」第3回は、経済産業省 商務・サービスグループ 消費・流通政策課長 物流企画室長 平林孝之様をお迎えし、持続可能な物流の実現に向けた政府の取組みや、2026年度から一定規模以上の荷主企業に選任が義務付けられるCLOの役割について考察します。
※本記事は2025年4月に行った取材をもとに構成しています。
物流改正法が示す、政府と事業者がともに目指すべき方向
引網 持続可能な物流の実現に向けて、2024年5月15日に物流改正法(※)が公布されました。なかでも「物資の流通の効率化に関する法律(改正物流効率化法)」は、荷主企業にとって今後の経営に大きな影響を与えると考えられます。2025年4月からの段階施行のポイントは何でしょうか?

平林 今年度の段階的施行の1回目では、基本方針、荷主・物流事業者の努力義務・判断基準等が示されました。2025年の秋頃には、取組み状況の把握に向け、荷主等の判断基準について物流事業者を対象とした調査を実施する見込みです。次に、2026年には2回目の段階的施行として、CLOの選任、中長期計画の作成や定期報告等が義務化されます。
荷主の皆さまにとっては、ここ1,2年の法的対応が一つの山になると感じています。物流改正法を実効的なものにするためには、民間事業者の皆さまと政府の双方で取り組むことが重要です。政府側は法律に対する認識を高めるための積極的な周知や広報、事業者のマインドをより前向きにする施策を打ち出すことにより、取組みを推進していくことがポイントと考えています。
引網 民間事業者としては、物流改正法で示されたわが国の課題感を自分事として捉え、取り組むことが重要ですね。当社では、昨年からお客様に向けて「CLOセミナー」を実施していますが、参加企業の方々とお話していて感じたことはありますか。
産形 印象的だったのは、製造業、流通業、小売業でも、CLOの管掌範囲であるサプライチェーンをすべからく把握するためには、様々な企業パートナーとの連携が必須ということでした。特に、食品関連のお客様は、業界における課題感を強く認識されていらっしゃるためでしょうか、物流改正法への取組み意識がとても高い印象です。総じて、「物流に関する取組みを前向きに行うべき」というポジティブな意見は強く、CLOを中心としてサプライチェーン全体を可視化しなければいけないという意識は高まっていると感じる一方、CLOの具体的な役割期待や人物像のイメージが湧かないという声も多く聞かれました。平林課長もおっしゃる通り、周知が進み、先行事例が出てくることで、事業者もより前向きに捉えられると思います。
平林 業種や業界によって様々な事情があると思いますが、サプライチェーン全体像の把握において、特に上流の「調達領域」の物流については、企業内の管轄部門が異なることなどからなかなか実態を掴み切れていないという製造業の課題は十数年前から言われてきました。そこで、「調達領域」から「販売領域」に至るサプライチェーン全体の最適化を一歩でも前に進めるために取り組んでいくことがCLOの役割だと考えています。
物流は「協調領域であり競争領域」
引網 物流における社会的な課題が広く認識された背景として、トラックドライバーの時間外労働の上限規制等が設けられた、いわゆる「2024年問題」が一つのきっかけでした。実際に、2024年以降に様々な影響が及ぶ「2024年から問題」とも言えますが、2025年のいま、どのように評価をされていらっしゃいますか?
平林 経産省としては「2024年問題」に対して荷主視点から取り組んでいます。事業者の皆さまのご理解とご協力により、今のところ懸念されたほどの深刻な問題は起きていないとの認識ですが、荷主事業者からは長距離輸送を断られた、納品期限を延長する事態が起きた、という話も聞きます。荷主側の物流への課題認識が深まってきている点はポジティブに捉えていますが、継続的な対策を講じないといずれ困難が生じるのは間違いありません。いずれにせよ、政府としては引き続き周知徹底を行い、事業者の皆さまには、さらなる改善を進めていただきたいと考えています。
引網 フューチャーアーキテクトが支援している顧客の方々も、物流のデジタル化で企業価値を高めようとされています。

産形 それぞれの荷主企業が自社なりの最適化を考えるときにきていると思います。例えば、これまでは「ジャストインタイム」が最適であるという見方がありましたが、例えばリードタイムを1日多くして、より多くの荷物をまとめて運ぶ方が効率が良いという見方もできます。また、小売企業では、需要予測を活用して店舗在庫を多めに保有し、混雑時の納品を避けるようにするなど、考え方が変化しつつあります。こうした新たな発想で物流最適化を実現するためには、自社の物流の実態が可視化できていることが必須です。当社のようなITコンサルティング企業の協力を得ながら、デジタルを駆使して物流の可視化を進めているお客様が増えています。
平林 物流とデジタルはとても相性が良いはずです。物流コストの削減が限界にくるなか、デジタルを活用した省力化に取り組むべき時代がきています。近年、スタートアップが次々と物流業界に新規参画しているのも、この分野に多くの課題とチャンスがあることの証左でしょう。
産形さんがおっしゃるとおり、サプライチェーンのヴィジビリティ(可視化)は非常に重要で、市場の動向に応じた調達、生産、販売を実現するには、どこにどれだけの在庫があるかをリアルタイムで把握し、最適な在庫を設定しなければなりません。それを実現するためのサプライチェーンの一元的な可視化の実現がCLOの役割の一つになります。まさに物流は協調領域と競争領域が表裏一体となる領域です。CLOには、商慣習の変革も含め、わが国の物流が直面しているリスクに対応し、企業価値向上につながるチャンスに変えることが求められています。
(※)流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
後編では、改正物流効率化法とデジタル活用について考察します。



