
2025.04.28
異分野コラボレーションによる共創|物流の未来をデザインする #2
大きな転換期を迎える物流業界。フューチャーアーキテクトでは、「物流×IT」で社会課題を解決することをミッションに、CLO(Chief Logistics Officer:物流統括管理者)の支援に取り組んでいます。
シリーズ記事「物流の未来をデザインする」第2回は、東京大学 先端科学技術研究センター 西成活裕教授をお迎えし、競合企業や異業種とのコラボレーションによる「持続可能な物流の共創」を実現するための仕組み作り・人材育成について考察します。
※本記事は2025年3月に行った取材をもとに構成しています。
まだ気づかれていない、物流という仕事の面白さ
引網 前回「CLOを支える高度物流人材」の記事では、CLOのミッションをチームとして実現する「高度物流人材」について議論しました。ここからは、「越境力」というキーワードを深掘りしていきたいと思います。
通常、業界のライバル企業が揃ってコラボレーションすることはあまりないですよね。しかし、ライバル企業と協調関係を築きながら課題解決をしていくことがミッションになっているのが物流という仕事の面白さです。

産形 私たちは、業界を超えたお客様同士の交流のきっかけを作ることも使命だと思っています。定期的にDXや物流関連の法改正をテーマにした経営者向けのプライベートセミナーを開催しているのですが、CLO向けセミナーでは、商社、卸、製造、小売等、発荷主と着荷主の分け隔てなく、様々なお客様に参加いただいています。
参加してくださった経営トップの皆さんは、まさしく西成先生が挙げてくださった「技術」「財務」「ビジネス」「倫理」の視点をお持ちです。物流課題を一社だけで解決しようとか、コスト目線だけで物流を評価しようといった考えではもはやない。業種・業界の垣根を超えて、デジタルを起点に新しい物流の仕組みを作っていこうという流れは確実に始まっていて、今こそ本当に面白い仕事ができる領域だと思います。
西成 優秀な人材でさえ、実はまだそこに気づいていないんです。物流はBtoBで、縁の下の力持ちの世界なので、特に学生の認知度はまだまだ低い。でも知らないだけなんです。今、様々な企業や大学にいる「関係者間の調整が得意な人」や「プログラミングが得意な人」が少しでも物流に興味を持ってくれたら、実現できる未来がすごく広がるだろうとワクワクします。

西成 例えば、物流倉庫は、実は理系の子にはたまらない世界なんです。倉庫にはロジック通りに動く部分もあり、フォークリフトや倉庫ロボットのような最新のマテハン機械が稼働し、それを設計する仕事もある。本当に魅力的な世界です。そして何よりも、物流は人に感謝される仕事ですよね。
引網 西成先生は5年前から、東京大学で先端物流科学講座を開いています。どのような授業をされているのでしょうか。
西成 数理最適化やAI、ドローンといった技術のプログラムはもちろんのこと、経済学部の先生も呼んで、経営や貿易についても講義してもらっています。
また、講義の半分は、物流会社や物流関連のベンチャーなどの事業者にスピーカーをお願いしています。学生には知識だけでなく、業界のしきたりや、変革に反対する人をどう説得すればいいかという合意形成論・倫理観を学んでもらいたいと思っています。世の中には、対立する意見をもった二人を仲裁するのがうまいような人がいますが、新時代の物流業界に求められているのはそういう人材だと思います。
物流の未来は、異分野コラボレーションの先にある
西成 学生だけでなく、大人も物流の面白さを知らない。日本ではまだ兼業を全面解禁している会社は少ないのですが、もっと自由に人材交流ができる仕組みにして、例えば、三か月だけどこかの物流センターで働いてみるとか、マトリクス組織を作ってみるとか、物流業界への人材の流動性を高める仕組みも必要だと思います。
産形 そうですね。我々の社内は半分がキャリア入社者なのですが、私たち物流グループには、フォークリフトを運転できる人、危険物を取り扱える人、物流センター長の経験がある人など、多様な人がいます。ITに強みを持つ会社という背骨はありつつも、専門性がひとつではなく複数あると、いろいろなコラボレーションがしやすい人材に成長できるというのは感じています。
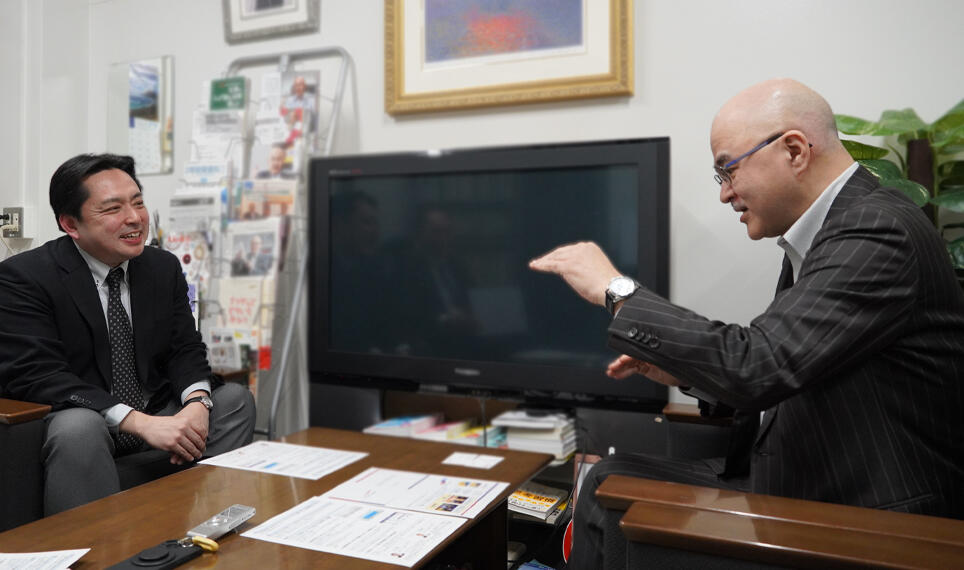
西成 今日はCLOというテーマで話をさせてもらいましたが、例えばCIOもテクノロジーだけを考えていればいいわけではないですし、CFOも財務ばかりを考えているわけでは決してないですよね。CLOも高度物流人材も、ロジスティクスに閉じない役割として、様々な活躍を期待します。
産形 物流業界はデジタル化が遅れている業界であり、だからこそ今後の成長の伸びしろも大きい仕事です。CLOのサポートができる人材を提供するということ、そして業界内の連携のきっかけとなる場を作り、人と人のつながりを広げていくことが私たちの使命だと改めて認識しました。
引網 西成先生、本日はありがとうございました。



